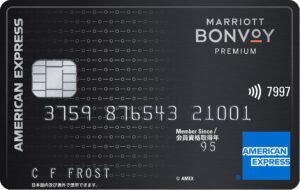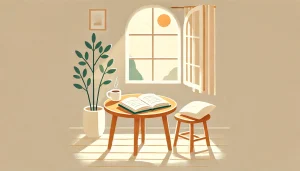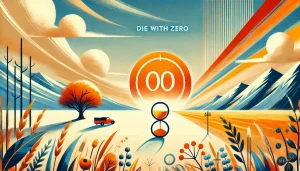みなさんこんにちは、わんだらです。近年、ハイテク銘柄の集合体とも言える「FANG+(ファングプラス)」は上下動を繰り返しながらも右肩上がりで成長してきました。しかし、最近の下落局面を目の当たりにすると、「ここからさらに下がるのでは?」「もう売り時かも…」と不安になってしまう方もいるかもしれません。
本記事では、FANG+の過去と現在を対数スケールで比較しながら、下落局面こそが“買い時”になり得る理由を解説します。また、投資信託を「口数」という視点で捉える重要性や、10年後に保有資産がどれほどの規模に成長しているかを、モンテカルロシミュレーションを用いた事例としてご紹介。さらに、2025年の米国株式市場のサイクル予測やビッグテックを取り巻くAIチャットボット市場の拡大など、最新の定量データも踏まえながら、長期投資のヒントをお伝えします。
「資産形成は長期勝負」「下落はむしろボーナスタイム」とはよく言われるものの、その本質をしっかり理解し、行動に移せるかどうかが成功の分かれ道。本記事を最後まで読んでいただければ、「なぜ下落相場でもホールドを続けるべきか」が腑に落ちるはずです。
FANG+の上下動から見る「買い時」とは
まず、FANG+の基準価格のチャートをざっと見てみると、2018年以降、上下動を繰り返しながらも長期的には右肩上がりで推移しています。発売開始からすでに7年以上経過しているため、決して「歴史の浅い指数」ではありません。
ただ、最近の下落幅がコロナショック時などと比べて大きいように見えるため、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、リニアスケール(通常の縦軸)で見ると急落が大きく見えるだけで、対数スケールで捉えると、過去にも同程度の下落は何度も起こってきたことが分かります。
- リニアスケール
縦軸を一定間隔で区切るため、価格が上昇すればするほど同じ下落率でも見た目の幅が大きくなる。 - 対数スケール
縦軸を割合(パーセンテージ変化)に基づいて表すため、長期間の分析に向いている。過去のコロナショックやインフレショック、リセッション懸念時の下落も含め、FANG+は一進一退を繰り返しながら成長してきた。
対数スケールで見ると、直近の下落はそこまで大きなものとは言えません。むしろ、FANG+が今後さらに上昇するための“健全な調整”と捉えることもできます。
投資信託は「口数」が重要
FANG+に限らず、投資信託を保有する際は「基準価格」よりも「口数」に着目するのが資産形成のカギになります。
- 基準価格
「1万口あたり」の価格を示す。たとえば基準価格が10,000円の場合、1口あたりの価格は1円という計算。 - 購入口数
「購入金額 ÷ 一口あたりの価格」で算出される。つまり基準価格が安いほど、同じ金額でより多くの口数を手に入れられる。
たとえば1万円分の投資で、基準価格が10,000円(1口あたり1円)の場合は1万口買えますが、基準価格が5,000円(1口あたり0.5円)の場合は2万口を買える計算になります。つまり下落相場は「一口あたりの価格が安い」状態なので、未来を見据えた資産形成期の投資家にとっては口数を積み上げられる大きなチャンスです。
10年後にFANG+はいくら?モンテカルロシミュレーションで試算
ここで気になるのが「10年後にはどれだけ資産が増えているのか」という点ですよね。たとえば現状、FANG+の一口あたりの価格が約6.5円だとすると、過去7年ほどのCAGR(年平均成長率)は約30%にも及びます。これをもとにモンテカルロシミュレーションを行うと、以下のような幅を持った結果が得られることがあります。
- 上位20%内の中央値: 1口あたり約180円超
- 全体の中央値: 約64円
- 下20%内の中央値: 約13円
もちろんシミュレーションなので確実ではありませんが、過去の成長率を踏まえれば「1口数十円~100円超」に化ける可能性も十分考えられます。仮に今、FANG+を数十万口保有しているなら、その評価額は何千万円から1億円を超える試算になるかもしれません。
2025年の相場はどうなる?サイクル予測と企業利益の見通し
◇ S&P500のサイクル予測
1928年から2024年までの米国株式市場を元にした「サイクルコンポジット予測」では、2025年のS&P500は年間を通じて上昇傾向が強いと示唆されるデータがあります。特に3月以降に上昇の勢いが高まり、4月や9月、11月には一時調整を挟みながら年末にかけて右肩上がりの展開を描く可能性が示されています。
◇ 企業利益の動向
一方で、S&P500全体のEPS予想は横ばい~微減の見通しがある一方、「マグニフィセント7」などのAI関連銘柄を中心にEPSが大幅プラスで引き上げられています。つまり、ビッグテックのような成長企業に資金が集中する流れが続く可能性が高いということ。FANG+のような指数には依然として魅力があると言えるでしょう。
AIチャットボット市場の急拡大とビッグテックの収益構造
AIチャットボット市場は、2024年には約155.7億ドル規模、2029年には約4,664億ドルに到達すると予測されています。企業が0からチャットボットを開発するには莫大なコストがかかるため、MicrosoftやGoogle、AmazonといったビッグテックのクラウドAIやAI APIを活用するケースが増えています。
- メリット
- 人件費削減、顧客満足度向上、24時間対応など
- デメリット
- 0からの開発コストが高額、継続的な運用が必須
チャットボット市場が成長すればするほど、クラウドサービスやAI APIを提供するビッグテック企業の収益は増加。この構造もFANG+などハイテク中心の指数が引き続き注目される一因になっています。
市場下落は避けられないが、それが資産形成のチャンス
過去100年近いS&P500のデータでは、年間3%の下落は平均7.2回、5%の下落は3.4回、10%の調整は1.1回という頻度で起こっています。つまり、「下落相場」は年に数回起こる“当たり前のこと”であり、長期投資を前提とするならば、ちょっとした調整で売り払うのは機会損失としか言えません。
むしろ、長期的に上昇する資産に投資しているのであれば、下落時こそ購入口数を増やすチャンス。このマインドを定着させ、「ジャストキープバイイング(JKB)」を続けられるかどうかが、資産形成の大きな分かれ道です。
健康あってこそ資産拡大を目指せる
最後に、資産形成と同じくらい大切な「健康管理」についても触れておきます。40代以上の方は特に、病気のリスクが高まる年代に差しかかっています。脳出血や心筋梗塞など、突然の病気は家族にとっても大きな衝撃です。
- 健康診断のオプション
- 会社で受けられるなら全身検査や脳の検査を検討
- 自費でもいいから1度は精密検査を受ける
資産がいくら増えたとしても、健康を失ってしまえば意味がありません。いざというときに後悔しないためにも、自己投資の一環として定期検査を受けることを強くおすすめします。
まとめ
FANG+やNASDAQ100などのハイテク中心指数はボラティリティが高い分、上下動が大きく、その過程で多くの投資家が不安を感じるでしょう。しかし、対数スケールのチャートや「購入口数」という考え方を取り入れると、下落相場ほど将来的なリターンを大きくするチャンスであることがはっきりします。
また、モンテカルロシミュレーションによる10年後の予測や、2025年のサイクルデータを参考にすれば、ポジティブに未来の成長をイメージできるでしょう。AIチャットボット市場の拡大など、ビッグテックを取り巻く環境は依然として明るい要素が多く、「JKB」を心がけながら積み立て投資を続けることが肝心です。
資産形成は「タイミング」よりも「タイム」。今すぐに大金が必要でなければ、焦る必要はありません。下落が訪れても買い向かい、保有する口数を着実に増やしていく。これこそが、大きなリターンを狙う長期投資家の王道と言えるでしょう。