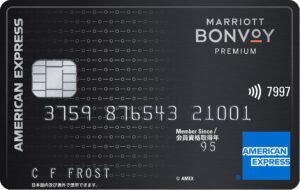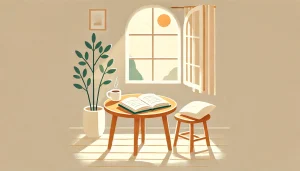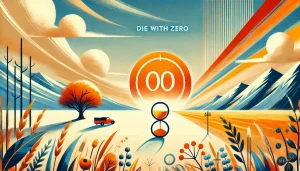みなさんこんにちは、わんだらです。新NISA(ニーサ)を活用して米国株や全世界株などにインデックス投資をしている方にとって、「いつ暴落が来るのか」という問題はどうしても気になるところですよね。実際に2025年に入って以降、株価がやや低迷している状況もあり、「大暴落が起こるのではないか」「景気の失速が近いのではないか」という声を耳にする機会も増えてきました。
もっとも、本当に近いうちに暴落が来るかどうかは誰にも分かりません。ですが、暴落は突然起こることが多いもの。そして、「暴落が起こったとき」に何も準備ができていないと、大きく資産を減らすばかりか、場合によっては取り返しのつかない失敗をしてしまう恐れすらあります。
そこで今回は、
- 暴落の歴史から分かる重要なポイント
- いつか来る暴落への備えとして理解しておくべき5つのこと
- 実際に行うべき具体的な対策
これらを中心にお伝えしていきます。この記事を読めば、長期投資を継続しやすくなり、資産形成を成功させるための心構えが身につくはずです。ぜひ最後までご覧ください。
1. 暴落の歴史を振り返る:愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉があるように、私たちが目先の値動きだけに囚われるのではなく、長期的な視点を持つためには過去の暴落を知ることが大切です。
1926年から2023年までの約97年間を見ても、米国株式市場には、
- マイナス20%以上の暴落が何度も起こっている
- 暴落後は数年をかけて徐々に株価が回復し、その後も成長を続けている
という歴史があります。実際、5年から10年周期で暴落が起こってきたデータもあり、「これから先も大きく下がることは普通にあり得る」ということを、まずは頭に入れておきましょう。
暴落の歴史から分かる3つのポイント
- おおよそ5年から10年周期で暴落が起こる
- 一度暴落しても、株価は時間をかけて必ず回復している
- 暴落後、元の水準に戻るまで平均3〜5年前後かかっている
この3点を知っているだけでも、相場が大きく下落したときに「いつかは戻ってくるかもしれない」という冷静な視点を持てます。とはいえ、人間の心理は弱いもの。本格的な下落や景気後退が起きると、不安を掻き立てる情報がメディアにあふれ、正しい判断がしにくくなります。
そこで次章では、「暴落が来る前に理解しておくべきこと」を5つご紹介します。未来の大暴落時に慌てず、コツコツと資産を形成していくためにも、あらかじめチェックしておきましょう。
2. 暴落前に理解しておくべき5つのポイント
2-1. 暴落は想定の範囲内である
インデックス投資は、期待リターンと同時にリスク(価格のブレ幅)もセットで考える必要があります。たとえば、全世界株式の期待リターンが年5%程度だとすると、
- リスクは年率15〜20%程度
- リスクの2倍、3倍を想定すると、一時的に最大30〜40%、あるいは50〜60%の下落が起こる可能性もある
という具合です。
実際にリーマンショック(2008年)では全世界株式の下落率が50%超だったため、「100年に一度の危機」と呼ばれました。
しかし、あらかじめ下落幅の目安を知っておけば、いざ暴落が来ても「想定外の事態だ」と慌てるリスクをグッと減らせます。
さらに、株式市場には「平均への回帰」という特徴があります。好調が続きすぎた相場は、いずれ平均リターン近辺に戻る動きが出やすいもの。2020〜2024年あたりは株価が総じて好調でしたが、その反動として下落が来る可能性は十分あるわけです。
要するに、「株価が落ちるのはあり得ることなんだ」と事前に分かっていれば、余計な失望や焦りを感じにくくなります。
2-2. 長期的な右肩上がりは揺らがない
過去の暴落を振り返ると、どれほど大きく下がったとしても、数年後には株価が持ち直し、さらに成長してきたという事実があります。大暴落が起こると「今度こそ世界恐慌クラスの不況だ」「資本主義が終わる」などと煽る情報が増えますが、そこにも冷静に反論できる理由があります。
- 景気や株価が大きく下がると、中央銀行が金融緩和を実施してお金の流通量を増やす
- 政府も減税や財政出動に踏み切って、経済を底支えする
歴史的にも、中央銀行が積極的に金利や通貨供給量をコントロールするようになったのは、世界恐慌の長期化などの失敗から学んだ結果です。現在、金本位制を採用している国はなく、各国とも状況に応じて金融政策を柔軟に行える仕組みがあります。よって、仮に一時的な大暴落や不況が起こっても、いずれは景気が回復して株価も再び右肩上がりになる可能性が高いのです。
2-3. 暴落を避けようとしてはいけない
株価が怪しい雰囲気になると、「一旦ファンドを全部売って、底値まで下がったら買い戻そう」と考える人は少なくありません。しかし、これは投資における大きな落とし穴です。
- 相場の「底」がいつなのかは後から振り返らないと分からない
- タイミングを図っているうちに急に反転上昇し、「稲妻が輝く瞬間」を逃してしまう
長期投資で最も避けるべきは、「最も大きな上昇の恩恵を受け損なう」ことです。実際、過去30年のS&P500(米国上位500社)の年率平均リターンは約11%ですが、投資家全体の実際の平均リターンは3〜4%台とも言われています。
これは「暴落を避けたい」「底値を狙いたい」といった心理からくる売買の失敗が原因。大事なのは、いつ何時も市場に居続けることです。サッカー漫画『キャプテン翼』で石崎君が「シュートを顔面ブロックする」ように、暴落も真正面から受け止めてしまうくらいの気持ちでいる方が、長期的な成績は向上しやすくなります。
2-4. 積立フェーズでは暴落がむしろ有利
新NISAを活用して積立投資をしている人にとっては、暴落は必ずしも悪いニュースではありません。むしろ、安く仕込むチャンスとも言えます。
以下は、株価が「① 右肩上がりのみ」の場合と、「② 途中で一度暴落してから上昇する」場合で、月3万円投資を行ったときのシミュレーション例です。
| ケース | 株価推移 | 毎月の投資額 | 購入できる株数 | 合計株数 | 最終株価時の評価額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 右肩上がりのみ | 1000円 → 2000円 → 3000円 | 3万円×3回 | 30株 → 15株 → 10株 | 55株 | 55株×3000円=16万5000円 |
| ② 途中で暴落 | 1000円 → 500円 → 3000円 | 3万円×3回 | 30株 → 60株 → 10株 | 100株 | 100株×3000円=30万円 |
暴落後にしっかり回復するという前提がある限り、下落しているときもコツコツ買い付けることで、より多くの株数を保有できるのです。よって、積立投資では株価の一時的な下落を「バーゲンセール」くらいに捉えるマインドが大切になります。
2-5. 地獄のような状況になるということを知っておく
実際に暴落や経済危機が起こると、メディアやSNSでは「令和恐慌が始まった」「資本主義はもう終わり」「インデックス投資はオワコン」など、不安を煽る情報が渦を巻きます。自分の資産がめべりする中でこういった声を見かけると、不安が増幅されるのは当たり前です。
しかし、もう一度思い出してみましょう。こうした「煽るような情報」には発信者の意図があります。たとえば、「過激なタイトルでPV数を稼ぎたい」「本を売りたい」といったビジネス上の目的があるかもしれません。
むしろ、「人々の欲望」が根底にあるからこそ資本主義は回り続けるわけです。悲観が極まったときには、案外そこが投資のチャンスになり得るケースも少なくありません。過去の大暴落の歴史でも、底値圏で買い続けた投資家が大きなリターンを得てきました。
要は、「地獄のような心理状態になり得る」という点を理解していれば、自分の気持ちが動揺したときに「これは想定どおりだ」と思えるのです。暴落の想定と資本主義の構造理解を両立させることで、長い目で見たときの資産成長に繋げることが可能になります。
3. 暴落への具体的な対策:長期投資を継続するために
「暴落がいつ来るのか?」については、正直いって誰にも分かりません。しかし、投資を続ける以上は「いつかは必ず暴落が来る」と考えておくほうが自然です。では、その日のために私たちは何を準備しておけばいいのでしょうか。ここでは、2つの具体的な対策をお伝えします。
3-1. リスク許容度を改めて確認する
リスク許容度とは、「どの程度のマイナスまでは自分が耐えられるか」を示す指標です。性格や年齢、収入状況、家族構成などによって大きく異なるうえ、非常に主観的なものでもあります。
ただし、ざっくりとした目安は、リスクの2倍〜3倍をマイナスとして想定したときに「どこまでならセーフか」で考えるやり方です。
たとえば、全世界株式のリスクを年率20%程度だと仮定して、
- 2倍:40%の下落
- 3倍:60%の下落
以上のような下落があっても最終的に耐えられる範囲で投資額をコントロールしておけば、暴落時に取り乱して致命的な損切りをするリスクが減ります。
もし今の投資金額が自分のリスク許容度を大幅に超えているなら、特定口座のファンドを一部売却したり、積立額を少し減らすなどの調整を検討しましょう。これだけでも、暴落時の精神的ダメージをかなり抑えられます。
3-2. 堅実な生活設計で不況にも強い家計に
暴落で最も怖いのは、資産評価額が下がることではありません。評価額が減るだけなら、株を売らずにホールドしておけば、いずれ回復するかもしれません。
本当に怖いのは、暴落をきっかけに不況が深刻化して、個人の収入まで大きく減ってしまうことです。給料のカットや失業リスクが高まる中、家計を維持できなくなり、やむなく投資資産を底値で取り崩すことになる可能性もゼロではありません。
だからこそ、今のうちに
- 支出のコントロール(無駄遣いを減らす、多額のローンを組まない)
- 収入源の分散(副業など、家計に複数のキャッシュフローを持たせる)
こうした対策を取っておくことで、景気が悪化しても生活防衛費を確保しつつ、積立投資を続ける余力を残せます。
4. まとめ:暴落を味方につけ、長期投資を成功させよう
いつ暴落が起こるのかは予測不能ですが、「いつか必ず起こる」という前提で動いたほうが、長期投資ではむしろ有利に働きます。大事なのは以下のポイントです。
- 暴落は想定内:リスクとリターンをセットで考え、下落幅を想定しておく
- 長期右肩上がりは揺るがない:歴史的に見ても株式市場は成長を続けてきた
- 暴落を避けようとしない:売買タイミングを狙うほどリターンが下がる
- 積立時は暴落が有利になることも:安く大量に仕込むチャンスになる
- 地獄のような情報氾濫を想定する:不安を煽るメディアに惑わされない
そして、いざというときに備えて、
- リスク許容度を再確認し、投資額を調整する
- 堅実な生活設計を行い、景気が冷え込んでも投資を続けられる体力を残す
こうした準備を今のうちにしておけば、仮に近い将来大暴落が訪れたとしても、慌てずに資産を守り、結果として長期的なリターンを最大化しやすくなります。
ぜひ、今回ご紹介したポイントを意識しつつ、一緒に長期投資・資産形成を続けていきましょう。