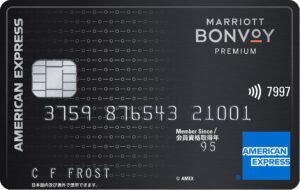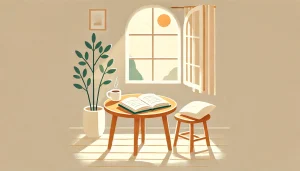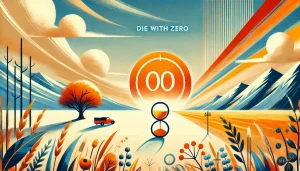みなさんこんにちは、わんだらです。近年、物価高や少子高齢化など暗いニュースが目立つ日本ですが、実は「富裕層」が増えているというデータが発表されています。大企業のサラリーマンや自営業者・投資家など、さまざまなバックグラウンドの人々が1億円以上の資産を保有し、いわゆる“富裕層”として認定されるケースが増加しているのです。
一方で、「海外移住をしないと資産形成は難しいのでは?」と考えている方も少なくないでしょう。確かに、ドバイやシンガポールなど税制やビジネス環境が有利な国々で活躍する起業家の成功事例が目立ちます。しかしながら、日本国内においても株式投資や不動産投資などを通じて着実に資産を増やし、“いつの間にか富裕層”になっている人たちがいるのも事実です。本記事では、野村総合研究所(NRI)が発表した日本の最新富裕層データを用いながら、その実態に迫ってみたいと思います。
2. 最新データが示す日本の富裕層ピラミッド
野村総合研究所では2年に一度、日本国内の世帯を金融資産額ごとに分類し、「富裕層ピラミッド」として公表しています。2023年版(2023年度調査)では以下の5つの層に分けられました。
| 階層 | 金融資産額 | 2023年推計世帯数 |
|---|---|---|
| 超富裕層 | 5億円以上 | 約11万8,000世帯 |
| 富裕層 | 1億円以上5億円未満 | 約153万世帯 |
| 準富裕層 | 5,000万円以上1億円未満 | 約403万世帯 |
| アッパーマス層 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 約576万世帯 |
| マス層 | 3,000万円未満 | —(全体の残り)— |
2021年度のデータと比較すると、以下のような変化が見られました。
- 超富裕層:+2万8,000世帯
- 富裕層:+4万世帯
- 準富裕層:+78万世帯
- アッパーマス層:-147万世帯
- マス層:+211万世帯
この2年間で、アッパーマス層だけが大きく減少している一方、超富裕層・富裕層・準富裕層は明確に増加しています。また、マス層(金融資産3,000万円未満)も増えているため、「中間層が減少し、富裕層とマス層の二極化が進行している」ことがうかがえます。
過去データとの比較で分かる傾向
さらに2005年からの推移を見てみると、超富裕層・富裕層の世帯数はほぼ2倍近くに増加しており、しかもその総資産額は約3倍にもなっています。一方で、アッパーマス層の数は減少し、総資産額もほぼ横ばい状態です。
要するに、ここ20年ほどで「豊かな人はより豊かに」「中間層は停滞」という構図がより鮮明化しているのです。
3. 増える新富裕層の背景と4つのタイプ
では、この10~20年の間で富裕層となった人々はいったいどのように資産を増やしてきたのでしょうか。大きく4つのパターンが考えられます。
- 投資で資産を拡大
- 株式投資:リーマンショック直後やコロナショック時に積極的に買い増しし、株価回復とともに大きなリターンを得た個人投資家
- 仮想通貨:2015年頃からビットコインやイーサリアムを保有し、価格高騰により莫大な資産を築いたケース
- 高収入サラリーマン
- 外資系企業やIT企業の幹部など、年収2,000万円超えのエリートがコツコツ資産運用も行い、最終的に1億円以上の金融資産を達成
- 事業成功者(起業家タイプ)
- ITスタートアップの創業者などが上場やM&A(事業売却)によって資産を一気に増やす
- 不動産や複数のビジネスを展開し、収益を多角化しているケース
- 相続による資産承継
- 元々資産家の家庭に生まれ、土地や賃貸不動産などを相続して資産が拡大
- 特に都市部の地主の子女や2世経営者などは、まとまった不動産収入を得やすい
4. 注目される「いつの間にか富裕層」と「スーパーパワーファミリー」
いつの間にか富裕層
最近増えているといわれるのが、野村総合研究所が「いつの間にか富裕層」と呼ぶタイプです。
- 特徴
- 元々それほど金融知識が高いわけではない
- 従業員持株会や確定拠出年金(DC)、NISA枠などを利用していたところ、株式相場の上昇で気づいたら1億円を超えていた
- 年齢は40~50代が多く、職業は一般のサラリーマンが中心
- 生活スタイルや消費行動は変わらず、“表面上は普通の生活”を送っている
こうした「いつの間にか富裕層」は、正確な金融商品の知識があまりないまま資産を増やしたことが特徴です。資産運用のリスクヘッジや分散投資の検討が不十分なまま高額資産を抱えているケースもあり、今後はより戦略的な資産管理が必要となるでしょう。
スーパーパワーファミリー
もう1つ注目されているのが、スーパーパワーファミリーです。
- 定義:都心部に住む、世帯年収3,000万円以上の共働き大企業勤務世帯
- 傾向:
- 20~30代の子育て期は出費がかさみ、資産形成しづらい
- しかし、キャリアアップや小・中学生の子供がある程度大きくなる頃には世帯年収が2,000万~3,000万円を超え、50代で富裕層になれる可能性が高い
- タワーマンションなど住宅の値上がり益が出る場合もあり、不動産資産の含み益が大きい
地方在住であっても、生活コストが都心より低いため、夫婦合計年収1,000万円程度でも十分ゆとりのある暮らしができ、60歳頃には資産1億円を視野に入れることも可能だといいます。
5. なぜ富裕層は増え、中間層は減るのか
今回のデータがはっきり示すように、日本ではかねてから指摘されてきた“中間層の減少と富裕層の増加”が、いっそう鮮明になりました。
- 理由1:株高や不動産価格の上昇
- コロナショック後の株式市場の回復、東京の都心を中心とした不動産市況の上昇など、資産バブルの恩恵を受けた人が多い
- 理由2:高収入共働き世帯の増加
- 女性の社会進出が進む一方、教育水準の高さも相まって夫婦ともに高収入を得る「スーパーパワーファミリー」が増えている
- 理由3:投資・金融リテラシーの拡大(部分的)
- NISAやiDeCo、確定拠出年金を利用するサラリーマンが増え、「いつの間にか富裕層」も出現
一方で、アッパーマス層が減少し、マス層が増える背景には、賃金の伸び悩みや、コロナ禍での収入減なども含まれていると考えられます。また、今後はインフレや税負担増などで生活コストが上昇し、資産形成のハードルがさらに高まる可能性もあるでしょう。
6. 日本で資産を増やすためのヒント:投資とレバレッジ活用
「富裕層になりたい」「中間層から抜け出したい」と考えている方にとって、過去の事例にはヒントが詰まっています。リーマンショックやコロナショックのような暴落相場でも買い増しを続ける投資スタンスや、銀行からの借り入れ(低金利)を活用した不動産投資が資産拡大に役立った例は多いです。
とりわけ日本の場合、低金利で銀行融資を受けやすいという環境が長く続いてきました。タワーマンションや地方の一棟物など、不動産価格が上昇傾向にあるタイミングを捉えれば、レバレッジ効果で短期間に大きく資産を増やせる可能性がありました。もちろん、今後も同じように値上がりが続く保証はありませんが、金融機関の活用や利回りの良い物件のリサーチは、引き続き有効な戦略といえます。
7. まとめ:海外移住しなくても資産形成は可能
- 富裕層は確実に増加し、格差の拡大は現実化
- 「いつの間にか富裕層」や「スーパーパワーファミリー」の存在感
- 低金利を活用した投資・不動産購入でチャンスは十分
海外移住をしなくとも、日本国内にはまだまだ資産形成の機会があります。もちろん情報収集や投資判断は自己責任ですが、行動することで10年後・20年後に思わぬリターンを得ることも十分可能でしょう。
なお、今回ご紹介したデータはあくまで過去から現在にかけての傾向を示すものであり、未来を約束するものではありません。しかし「富裕層が着実に増えている」事実は、少なくともこれから資産を増やしたい方にとって大きな希望につながるはずです。