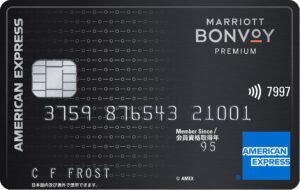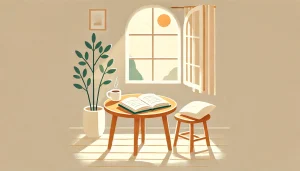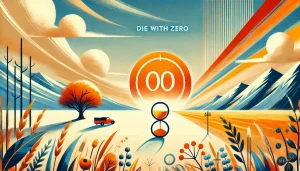みなさんこんにちは、わんだらです。今回は「“買ってはいけない非効率な投資10選”」というテーマでお話しします。多くの方が資産運用で「豊かな人生を送りたい」「老後の不安を減らしたい」と考えていると思います。しかし、投資の世界に100%必ず成功する絶対的な方法などありません。むしろ「これをやると非効率になりやすい」というものを避けるだけで、資産運用の成功確率を大幅に上げられるのです。
本記事では、「買ってはいけない非効率な資産運用10選」を紹介します。投資初心者の方ほど、ここで解説するポイントをぜひ押さえておいてください。なお、すべての人に100%当てはまるわけではありませんが、最大公約数的な視点から見て9割方は該当すると思います。ぜひ今後の資産運用に役立ててみてください。
1. 円預金との抱き合わせ販売
円預金+外貨預金や投資信託の“お得な”キャンペーンに注意
最近は「高金利の円預金」と「外貨預金」または「投資信託」をセットにする抱き合わせプランがよく見られます。一見すると「円預金で2%の利息がもらえる!」など魅力的に映りますが、その裏には金融機関にとって利益率が高い商品をセット販売する目的があります。
具体例
- 外貨預金と高金利円預金のセット
- 「米ドル預金を一定額預けると、その同額の円預金を〇%で運用できます」というキャンペーン。
- しかし、別々に(ネット銀行の高金利円預金+他社の外貨建てMMFなど)組み合わせたほうがトータル利回りが高いケースも多いのです。
- 投資信託と定期預金のセット
- 「投資信託を1,000万円以上購入すると、3ヶ月間だけ円定期預金が5%になる」など。
- ただし、購入時手数料が高いファンドしか対象でない場合が多く、高い円定期の裏で大きなコストを支払わされる可能性があります。
抱き合わせキャンペーンは、「投資家が思わず飛びつく好条件」を提示して注意をそらし、実は手数料の高い商品を紛れ込ませているケースが多いのです。メリットとデメリットをしっかり比較し、本当に自分にとって得かどうか吟味しましょう。
2. 仕組み預金
「預金」とは名ばかりのリスク商品
仕組み預金はデリバティブ取引を活用した複雑な金融商品で、途中解約時に大きく元本割れが起こる可能性があります。
代表的なタイプ
- 満期の時期が変わるタイプ
- 金融機関側が「商品をいつ召喚するか」を決められる。
- 例えば最初は金利がそこそこ高く設定されていても、投資家が得をしそうなタイミングで早期に召喚されるため、高い金利を満額受け取るのは難しい。
- 満期時の受取通貨が変わるタイプ
- 一定の為替条件を超えなければ高い金利がもらえず、さらに受取が外貨に変わることで損失リスクを抱える。
- 例えば「条件を満たさなかったら米ドルで戻ってくる」という形。想定より円安が進まなかったりすると結局は損失を被る。
金融機関が巧妙に計算し、長期的に見れば金融機関が必ず手数料を得る構造になっています。投資初心者にはハードルが高く、「預金」という名前だけで安心しないことが重要です。
3. 仕組み債
株式のリスクで、債券程度のリターンしか得られない商品
仕組み債も仕組み預金同様、デリバティブを用いて「条件を満たせば高めの金利、下回れば元本割れ」といった複雑な設計を持ちます。
- 一例としては「日経平均とS&P500が一定水準より下がらなければ、毎年3%受け取れる。だが、そこを下回ったら大きく元本割れする」といったもの。
- しかも、投資家に有利な状況になると「早期召喚」という形で強制的に終わらせられる場合が大半です。
- 証券会社はロール(再購入)を繰り返すことで、販売のたびに5%程度の手数料を得る構造になっています。
まとめると、**「株式並みのリスクを負っているのに、受け取れるリターンは債券並み」**という非効率な商品。プロの世界ではオーダーメイドで使うこともありますが、初心者が手を出すには危険です。
4. ネット証券では0円なのに購入手数料がかかるもの
販売会社によってコストが違う不思議
同じ国内株式や同じ投資信託でも、販売会社がどこかによって手数料が大きく変わるケースがあります。
- 国内株式なら、ネット証券(SBIや楽天証券など)だとほぼ手数料が0円。
- 一方で、大手対面証券だと1%前後の売買手数料がかかる場合がある。
投資信託も同様
- 楽天証券だとノーロード(購入手数料0円)で買えるファンドでも、他社では2%や3%の手数料がかかることも。
- 商品(銘柄)は同じでも、販売会社の違いでコストが変わる点には注意しましょう。
特にインデックスファンドが普及している現在では、購入手数料無料のファンドが増えています。しかし、まだまだ注意すべき銘柄も残っているため、買う前に「手数料無料かどうか」は必ず確認するのがおすすめです。
5. ファンドラップ
年間2%前後かかるコストは重い
ファンドラップ(投資一任口座)とは、投資家が資金を預けると金融機関が分散投資・リバランスを代行してくれるサービス。年々利用者数が増え、国内のファンドラップ残高は2024年末時点で21兆円超ともいわれています。
ファンドラップが非効率になりやすい理由
- コストが高い
- 委託手数料(1~2%前後)+投資対象ファンドの信託報酬(0.5%前後)で、合計2%ほどになるケースも。
- 投資家ごとにオーダーメイドといっても、実態は数パターンに分類されるだけ
- 「慎重型」「やや積極型」など数種類のモデルポートフォリオから選ばれるに過ぎず、きめ細かい対応ではない場合も多い。
初心者が最初の数年だけ「投資に慣れるために使う」のは一案ですが、長期的には自分で低コストファンドを組み合わせたほうが有利と言えるでしょう。
6. 毎月分配型ファンド
複利効果を最大化できず、コストも割高
毎月分配型は、その名の通り毎月ファンドから分配金が支払われるタイプ。しかし、この仕組みは下記のようなデメリットがあります。
- 税金負けが大きい
- 分配金の20%は源泉徴収される。結果、複利効果が失われる。
- タコ足配当の可能性
- 利益が出ていないのに無理やり分配金を出す場合は「自分の元本を切り崩しているだけ」に過ぎない。
- 毎月決算で手間がかかる
- 年1回決算のファンドに比べ、決算関連コストが多くなりやすい。
「毎月お金がほしい」なら、自分で必要な分だけファンドを売却して取り崩すほうが合理的です。それでも毎月分配型ファンドは一定の人気がありますが、長期投資では非効率と覚えておきましょう。
7. 投資目的の生命保険
保険は保証、運用は証券で──が基本
日本人は生命保険が大好きと言われますが、投資目的で保険に入るのはおすすめできません。
生命保険の2種類
- 貯蓄型保険(就寝保険、学資保険、個人年金保険、変額保険など)
- 掛け捨て型保険(掛け金が返ってこないタイプ)
貯蓄型保険は、保証と運用を混ぜ合わせた商品です。実際には保険料の中に高額な手数料が含まれており、外貨建て保険などは5~7%ものセールスコミッションが抜かれることも珍しくありません。
- 保障が必要なら、掛け捨て型の方がコストが安い。
- 運用はNISAやiDeCoなどで低コスト投信に回すほうが効率的です。
ただし「相続税対策としての生命保険」など、別の目的で貯蓄型保険が活用されるケースもあります。そこは個々人の状況によるので、十分に検討した上で加入を判断しましょう。
8. 新築ワンルームマンション投資
業者にとっては高利益、投資家にとっては出口が厳しい
不動産投資自体は悪くありませんが、特に新築ワンルームマンションは多くの投資家が後悔しやすいと言われます。
新築ワンルーム投資のデメリット
- 出口戦略の難しさ
- ワンルームを実需で買う人は少なく、売却先は投資家に限られる。結果、需要が絞られ価格交渉で不利に。
- 高額な利益(キックバック)構造
- 新築ワンルーム業者は1件売るごとに数十万円以上のマージンを得る。紹介者にも多額のキックバックが支払われる。
- そうしたコストを購入価格に上乗せしているため、投資家は不利になりやすい。
著者自身も昔、新築ワンルームマンション投資で後悔した経験があります。「営業トークに押されて買ったけど、出口が見えない…」という声はよく聞くので要注意です。
9. 新興国債券
高金利に惑わされないで
南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ブラジルレアルなど新興国通貨建ての債券は、一見すると利回りが8~10%以上と非常に魅力的に映ります。トルコリラに至っては表面利回りが40%を超えるケースもあります。
しかし、このような高金利通貨はインフレ率も高く、通貨価値が下落しやすい特性があることを忘れてはいけません。
- 例:トルコリラはかつて1リラ=100円近辺だったものが、現在は4円以下(1/25)程度まで下落。
- 高い金利を得ても、為替差損が大きければトータルリターンはマイナスになるリスク大。
- 為替スプレッドが大きく、取引コストも高い。
知識と経験があれば狙っても構いませんが、投資初心者は回避するのが無難です。
10. 運用成績が悪いアクティブファンド
すべてのアクティブファンドがダメなわけではないが…
アクティブ型ファンドとは、S&P500やTOPIXなどの指数を上回るリターンを狙う投資信託。とはいえ全体の8割前後がインデックスに負けるというデータもあり、手数料が高いにもかかわらず、実際にはインデックスファンドに劣るケースが多いのが現実です。
アクティブ投信の注意点
- コスト(信託報酬)が高い
- 実績(トラックレコード)は最低5年は見たほうがよい
- 過去に勝っていても将来も勝つとは限らない
もっとも、アクティブ運用の中にはヘッジファンドのように高いリターンを出す例外もあります。ただし一般公募型のアクティブファンドの大半はベンチマークに負けがちです。特に運用成績が悪いのに高コストなファンドは避けたほうがよいでしょう。
11. まとめ:理解できない商品には手を出さない
ここまで「買ってはいけない非効率な資産運用10選」を紹介しました。いずれも9割の投資家には当てはまると言っても過言ではないものばかりです。最終的に、資産運用の大原則はやはり「自分が理解できない投資商品には手を出さない」ことに尽きます。
投資商品を誰かに説明しようとした時、スラスラと「なぜこの商品なのか」「どういうリスクがあるのか」と説明できないのであれば、それはまだ理解が足りない証拠です。
もちろん商品によっては複雑だからこそ価値があるケースもあります。しかし、レバレッジやデリバティブを使いこなせるほど投資経験があるかどうかが重要です。自分がまだ理解できないと思うなら、いったんは見送り、自分の知識が追いついてから再度検討しても遅くはありません。
【ポイント】
- 王道のインデックスファンドや低コスト商品から始めれば、初心者でも安定して資産形成を進められます。
- 仕組みが複雑な商品には、往々にして金融機関の高い利益が隠れている。
- 「運用」と「保証」は切り離す──保険商品を使って運用するのではなく、掛け捨て保険+証券口座での運用が基本。
投資を続けながら、知識を一つひとつ積み上げていけば、自分の扱える“武器”も広がっていきます。慣れたらアクティブファンドも検討する、というふうに段階を踏むことで、より戦略的に資産形成を行えるでしょう。
【参考資料に関する補足】
- 新築ワンルームマンション投資や仕組み預金などは、過去に何度か社会問題化してきた経緯がありますが、また手を変え品を変え販売される可能性も十分あります。常に最新情報を確認し、自分が納得できる投資を心がけましょう。
- ファンドラップや毎月分配型ファンドなどは「初心者にも分かりやすい運用を実現する」というPRがなされがちですが、その裏のコスト構造を必ず確認してください。
【図表・グラフのイメージ】
- 高コスト商品の例(イメージ表)
| 商品名 | 年間コストイメージ(%) | 主なリスク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仕組み預金 | 1~2%以上(※) | 元本割れ、早期召喚 | デリバティブによる設計 |
| ファンドラップ | 2%前後 | 市場リスク | 二重手数料がかかる |
| 毎月分配型ファンド | 1~2%前後+税金 | タコ足配当、複利効果喪失 | 決算回数が多い |
| 投資目的の生命保険 | 実質5~7%の初期手数料 | 為替リスク(外貨建ての場合) | 保険+投資の複合 |
(※)金融機関による手数料構造は複雑で、一概には言えません。
- インデックス投資 vs アクティブ投資のパフォーマンス比較(概念図)
- 棒グラフや折れ線グラフなどで、大半のアクティブファンドがベンチマークに及ばない傾向を示す。
- ただし、ほんの一部にはベンチマークを大きく上回る“優秀なアクティブファンド”も存在する。
【よくある質問(FAQ)】
Q1. それでも外貨預金はやめたほうがいいの?
A. 一概にNGとは言えませんが、外貨MMFや外国債券ETFなど他の選択肢も検討してみてください。同じ為替リスクを背負うなら、コストが安く利回りが高い商品があるかもしれません。
Q2. 毎月分配型でも優秀なファンドはある?
A. 運用実績が高く、分配方針も適切なファンドは存在しますが、基本的に毎月分配型ファンドは複利効果を損ねやすい構造です。長期投資が目的なら避けたほうが無難でしょう。
Q3. 仕組み債や仕組み預金は必ず買ってはいけないの?
A. 必ずしもダメとは言えませんが、仕組みを理解しないまま買うのは危険です。デリバティブ取引の基本を理解した上で、リスクを承知して投資できる上級者向けと言えます。