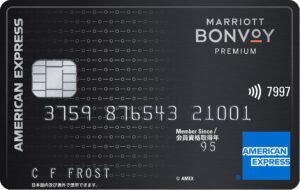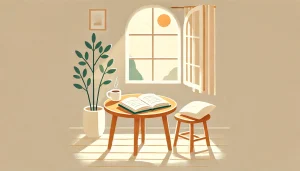みなさんこんにちは、わんだらです。タイトルにある「富裕層」と聞くと、どこか雲の上の存在のように感じる方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、日本には1億円以上の資産を持つ世帯が約2.8%存在しています。街を歩けば50世帯に1世帯ほどが“1億円以上”と考えると、意外と身近に感じられるかもしれません。
本記事では、野村総合研究所が公表している「準金融資産」に基づく資産の階層区分から、日本の富裕層の構成比率やその推移、そして将来的にアッパーマス層や準富裕層を目指すためには何をすればよいのかを解説します。さらに、上位層がどのような職業や背景を持っているのか、日本に眠る1,000兆円の個人資産が動き出した場合の可能性などにも触れ、投資を含めた資産形成のヒントをお伝えします。
1. 富裕層を区分する「準金融資産」とは?
まず、「富裕層」とはどのように定義されているのでしょうか。野村総合研究所のレポートによると、資産の階層は以下のように分けられています。
- 準金融資産
預貯金・株式・保険などの資産から、不動産や借入れなどの負債を差し引いた純粋な金融資産に近い指標が「準金融資産」です。 - マス層
準金融資産が3,000万円未満の世帯。 - アッパーマス層
準金融資産が3,000万円以上5,000万円未満の世帯。 - 準富裕層
準金融資産が5,000万円以上1億円未満の世帯。 - 富裕層
準金融資産が1億円以上5億円未満の世帯。 - 超富裕層
準金融資産が5億円以上の世帯。
こうして見ると、「1億円以上の富裕層」と「5億円以上の超富裕層」は、生活感からかけ離れた数字にも思えます。しかし、実際に日本にはそれぞれ約149万世帯(全体の2.8%)が存在すると言われています。
2. 富裕層ピラミッドの実態:1億円以上はたった2.8%
富裕層・超富裕層の割合
- 富裕層・超富裕層(1億円以上)
→ 約149万世帯(全体の2.8%)
この2.8%という数値は一見すると少ないようにも感じられますが、街中で50世帯に1世帯程度が該当する計算になります。思いのほか身近に存在しているといえるでしょう。
その他の層の割合
- 準富裕層(5,000万円~1億円)
→ 約325万世帯(全体の6%程度) - アッパーマス層(3,000万円~5,000万円)
→ 約726万世帯(全体の13%程度) - マス層(3,000万円未満)
→ 約4,213万世帯(全体の78%)
こうして見ると、最も多いのは「マス層」で全体の78%を占め、次いでアッパーマス層、準富裕層、そして最上位に富裕層・超富裕層が続く形になります。
ピラミッドでは見えない富裕層・超富裕層の“実数”
金融資産ピラミッドは図にすると上部が小さく見えますが、実際には2.8%の世帯が1億円以上の資産を持っていることになります。さらに5億円以上の「超富裕層」は全体の中でもごく一部ですが、この層のなかには著名経営者や上場企業役員、医師、弁護士、投資家などが含まれているのです。
3. マス層を脱却するには?アッパーマス・準富裕層への道
積立投資でアッパーマス層を目指す
「経営者や弁護士、医師のような資格がないと富裕層にはなれないのでは?」と感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には投資によって上の層へステップアップすることも可能です。
たとえば、月6万円を年利5%で積み立てたとしましょう。複利の効果を考慮すると、約22年後に3,000万円以上の資産(アッパーマス層)を達成できる試算になります。アッパーマス層は日本の上位25%ですから、決して夢物語ではないといえます。
準富裕層(5,000万円以上)を目指すには
さらに、同じく月6万円を年利5%で続けると、約30年で5,000万円に到達し、準富裕層の仲間入りを果たすことも可能です。準富裕層は日本の上位10%に入る世帯ですから、大きな目標となるでしょう。
1億円を視野に入れるなら
もちろん、1億円の資産を目指す場合には、単純に月12万円を積み立てるなど、よりハイペースな投資が必要です。また、運用利回りが平均5%を下回れば達成時期は遅れますし、逆に5%を上回れば早まる可能性もあります。いずれにしても、投資を軸に資産形成を図ることが、マス層から脱却する一つの道といえるでしょう。
4. 円の価値低下と世界の富の偏在:上位10%が76%を保有
日本国内での富の集中
野村総合研究所の試算によると、富裕層(1億円以上)と超富裕層(5億円以上)のたった2.8%の世帯が、日本全体の金融資産の約22%を所有しています。数値だけ見ると「なんだ、22%ならそれほどでもないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、上位2.8%が全体の2割以上を占めるというのは決して小さくないインパクトです。
世界規模での富の集中
さらに視野を広げると、世界の上位10%の富裕層が全体の76%もの富を保有しているというデータもあります。イーロン・マスクやウォーレン・バフェットなど、世界的に著名な資産家が膨大な富を蓄えている現状は、ニュースやSNSでもしばしば話題になります。
円安やインフレとの関係
近年は円安やインフレ傾向が加速しています。円の価値が下がると、相対的に海外資産への投資やドル資産の重要性が増し、ますます資産格差が広がる要因となるかもしれません。一方で、長期的には資産運用に取り組むことで、その恩恵を受ける可能性もあるため、早めの対策が大切です。
5. 上位階層が増加している理由と日本経済の強み
富裕層・超富裕層が増えている背景
野村総合研究所のデータによると、5億円以上の超富裕層と1億円以上の富裕層、そして5,000万円以上の準富裕層はいずれも増加傾向にあります。一方で、アッパーマス層(3,000万円~5,000万円)やマス層(3,000万円未満)は減少しています。
これには、株式市場の上昇や不動産価格の高騰、事業による成功などが要因として挙げられます。また、円安が進むことで海外から見た日本企業の割安感が高まり、海外投資家の資金流入が増えている点も、富裕層の拡大を後押ししている可能性があります。
日本の強み:インバウンド・食文化・アニメ・宇宙分野
日本には、世界に誇る強みがいくつも存在します。たとえば、
- インバウンド(訪日外国人)需要の増加
- 食文化の多様さ
- アニメやゲーム産業の国際的人気
- 宇宙分野への投資拡大
さらに、日本は世界最大級の対外純資産を保有している国です。これらの要素が、今後の経済成長を支えるポテンシャルになると期待されています。
日銀のETFやインフレ時代の追い風
- 日銀のETF分配金収入は年間1兆円以上ともいわれ、金融政策も含めて株式市場を支える要因となっています。
- 近年はインフレ時代への突入もあり、実物資産や株式に資金が流れ込みやすい環境が続いています。
こうした背景から、日本における富裕層の増加が今後も続く可能性は十分にあるでしょう。
6. 1,000兆円の個人預金が動くとき:投資の未来は明るい?
眠る1,000兆円のインパクト
日本国内の個人が保有する現金・預金は、およそ1,000兆円と言われています。一方で、株式や投資信託などのリスク資産に回っているのは300兆円程度。もしこの1,000兆円のうち、ほんの一部でも株式市場や投資信託に流れ始めたとしたら、相場の大きな上昇要因になるかもしれません。
金融所得課税強化の懸念
しかしながら、政府が示唆している金融所得課税の強化が進めば、投資に対するインセンティブが削がれる可能性もあります。仮に税率が上がれば、投資家の利益が縮小するため、1,000兆円が市場に流れにくくなる恐れも指摘されています。
アメリカのMMF残高も過去最高
一方、海外に目を向けると、アメリカではMMF(マネー・マーケット・ファンド)の残高が過去最高水準に達しています。リスクオフな資金が溜まっている状況ですが、市場の好転によって大きく流出(株式市場に投資される)可能性もあるため、将来的には相場の上昇を後押しする材料となるかもしれません。
7. まとめ:富裕層を目指すために今できること
本記事では、日本の富裕層と超富裕層の割合や、その背景、そして投資を通じて上位層を目指す方法を解説してきました。改めてポイントを振り返ってみましょう。
- 富裕層・超富裕層は全体の2.8%で約149万世帯
- 少数ながら、街を歩けば50世帯に1世帯は1億円以上という計算。
- マス層(3,000万円未満)が約78%と最も多い
- 一方で、月6万円の積立投資を年利5%で続ければ、約22年でアッパーマス層(3,000万円以上)も可能。
- 富裕層への道は「投資」を軸に狙える
- 経営者や専門職だけでなく、コツコツと投資を続けることで資産を築くことは十分に可能。
- 日本国内に眠る1,000兆円のインパクト
- もしこれが動き出せば株式市場には大きな追い風。
- ただし金融所得課税強化の動向など、政策リスクにも注意が必要。
- 日本の強みとインフレ時代
- インバウンドやアニメなどの成長産業、日銀のETF買い、インフレによる株式資産価値の上昇など、富裕層がさらに増える可能性あり。
最終的に、マス層からアッパーマス層、準富裕層、そして富裕層へとステップアップするためには、長期的な投資の継続と資金管理の徹底が欠かせません。特に複利の力は偉大で、コツコツ積み立てることで将来的に大きなリターンを得られる可能性があります。
今後、円安やインフレ傾向が続けば、さらに資産形成の重要性が増していくことでしょう。まずは自分の収支や投資の目的をしっかり見直し、無理のない範囲で積立投資を始めることが、富裕層を目指す第一歩になるはずです。
参考データ・関連キーワード
- 野村総合研究所「世帯の金融資産保有額調査」
- 富裕層・超富裕層・準富裕層・アッパーマス層・マス層
- 金融所得課税強化、インフレ、円安、インバウンド
- 月6万円積立、年率5%、複利効果
- 1,000兆円の個人預金、海外投資家、MMF過去最高
今後の展望とアクション
日本には、「1万円札が入った財布が5,000円で買えるくらい安い株」と形容されるほど割安な銘柄も存在します。投資の未来は明るいとされる理由の一つです。とはいえ、投資にはリスクがつきもの。大切なのは、リスク管理をしながら長期視点で資産を育てることです。
今後も富裕層や超富裕層は増加する見込みがある一方、マス層が減少していることも事実です。あなたがもし資産形成に興味を持ち、投資を始めているのなら、すでに「上の階層」へ近づく第一歩を踏み出しているといえます。ぜひ、無理なく続けられる方法で、コツコツと資産を増やしていきましょう。