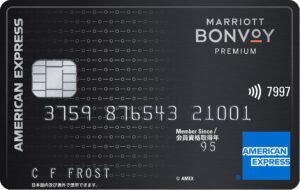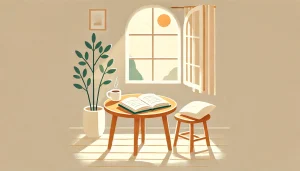みなさんこんにちは、わんだらです。ここ数年で投資に対する注目度は飛躍的に高まりました。特に2024年初頭から始まった「新NISA」への期待感から、証券会社の口座開設数が急増し、日本でも「投資を始めよう!」という機運が盛り上がっています。
実際、現金信仰が根強い日本において「資産運用」という概念が少しずつ浸透しはじめていることはとても素晴らしいことです。さらに、人気ランキング上位の商品を見ても、全世界株式や米国株式に分散投資するインデックスファンドが独占状態となっており、「長期投資でコツコツ積み立てる」ことを実践している投資家が増えているのは有望な流れだといえます。
ところが、実際にはほとんどの人が長期投資を継続できないというデータがあります。たとえば、自由に売却が可能なNISA対象商品の「平均保有年数」は2年程度、投資信託全体でも2.5年程度で手放してしまうケースが多いのです。
「20年、30年先を見据えた投資」だと意気込んでスタートしても、気づけば売却してしまい退場する──こんな状況がなぜ起こるのでしょうか?
本記事では、投資初心者が長期投資をやめてしまう5つの理由を整理しながら、その対処法と心構えを詳しく解説していきます。最後までお読みいただければ、長期投資を継続しやすくなり、資産形成への自信をより深められるはずです。
1. 投資を継続できない理由1:毎年資産が増え続けると誤解している
シミュレーターの「美しい曲線」に騙されるな
NISAや積立投資を始める際、証券会社や各種金融庁のシミュレーターを使って「年間○%のリターンで×年運用すると、資産はこんなに増えます!」といったグラフを目にすることが多いでしょう。
しかし、この「なだらかな右肩上がりの曲線」を現実の値動きだと思い込んでしまうと、「実際に投資してみたら、全然グラフどおりにならない…」とショックを受け、大きな下落局面で投資をやめてしまうケースが少なくありません。
実際の株価は“上下変動の連続”
たとえば、全世界株式ETFとして有名な「VT」のチャートを見ると、設定直後にリーマンショックがあり、一時は大幅下落しました。しかし、長い目で見ると年利6%前後のリターンを達成しています。
投資のリアルな値動きは、シミュレーションの曲線とはまったく違い、日々上下動を繰り返しながら、最終的に「平均年利○%」に落ち着くことが多いのです。
結論:下落があるのが当たり前
毎年必ず資産が増えるわけではなく、むしろ短期的には下落があって当然。それでも長期で見ればプラスに落ち着く可能性が高いからこそ、インデックス投資が有効とされています。
シミュレーションはあくまで「20年後、30年後を俯瞰するためのざっくりイメージ」に過ぎず、短期的な株価の乱高下はつきものだと、最初から理解しておくことが大切です。
2. 投資を継続できない理由2:含み損を“現実の損失”と捉えてしまう
インデックス投資の含み損は“幻”?
投資の世界では「含み益は幻、含み損は現実」と言われることがあります。しかし、インデックス投資においては含み損であっても、“幻”と割り切って問題ないのです。
なぜなら、長期投資前提のインデックスファンドは「どの企業が伸びるかを予想せず、市場全体に投資する」という手法。短期的に売り買いを繰り返す目的ではないため、「損切り」をする必要性が極めて低いからです。
含み損=安く買い増せるボーナスタイム
たとえば、毎月定額を積み立てる“ドルコスト平均法”の場合、一時的に株価が下落している時期のほうが安く多くの口数を買えるチャンスになります。
「評価額がマイナスになっている…」と焦るのではなく、
「お得に仕込める絶好のタイミングがきた!」
とポジティブに考えることこそ、長期投資家の発想です。数年後・数十年後に株価が戻っていれば、むしろ含み損期間が長いほうがリターンが大きくなる可能性すらあるのです。
生活防衛資金を確保することが前提
もちろん、どうしても売却が必要になるときに含み損を抱えていると、それは実損になってしまいます。そこで重要なのは、生活防衛資金を別に用意しておくこと。
近い将来使う予定があるお金(子どもの学費や引っ越し資金など)は投資に回さず、なくなっても当面困らないお金だけを長期投資に回す。こうすることで「含み損を耐える」必要がほぼなくなるのです。
3. 投資を継続できない理由3:投資対象への理解不足
「YouTuberが言っていたから買う」は危険
今は多くの投資系YouTuberやSNSインフルエンサーが存在し、初心者にとっては情報を得やすい反面、投資対象に対する深い理解がないまま銘柄を買ってしまう人が増えています。
いざ相場が下がると「○○って人が推奨してたのに損してるじゃないか!」と感情的に売却し、投資をやめてしまうケースが代表例です。
目論見書・組入銘柄の“中身”を知る
投資信託なら「目論見書」や「運用報告書」をチェックし、自分がお金を預けているファンドの組入銘柄や投資先の国・セクターをざっくりでも理解しておきましょう。
たとえば、
- オルカン(全世界株式)を100万円分持っているなら、MicrosoftやApple、NVIDIAなど、世界を代表する企業の株主になっている
- アメリカやヨーロッパの一流企業だけでなく、日本や新興国も含めて分散している
といった事実を知るだけでも心持ちは大きく違います。
自分の会社よりはるかに強い企業への投資
一般的なサラリーマンが勤めている企業よりも、世界の有名企業のほうが倒産リスクは低いというケースは少なくありません。むしろ1社に勤めるリスクのほうが大きい、と捉える投資家もいるくらいです。
こうした知識を得れば、「株価が下がったらどうしよう…」という不安は和らぎ、長期目線で投資を続けられるようになります。
4. 投資を継続できない理由4:オーバーコンフィデンス(自信過剰)
男性ほど陥りやすいデータも
アメリカの研究では、男女の投資パフォーマンスを比較したとき、女性投資家のほうがリターンが年率1%程度高かったという報告があります。理由として、男性のほうが自信過剰になりがちで、無駄な売買を繰り返し、手数料負けしてしまう傾向が指摘されています。
“自分は人より勝てる”が招く大損
「自分は投資の才能がある」「相場の天井と底をピタリと見極められるはず」という思い込みこそが、退場につながる大きな要因です。
- もっとリターンを狙えるはずだと、ハイリスク商品の集中投資をしてしまう
- 信用取引やレバレッジ取引などで、大きく負けたときに立ち直れなくなる
- タイミング投資(相場の上がり下がりを短期的に予想)に走ってしまい、結局は上昇局面に乗れず取り逃す
といった事態を引き起こしがちです。
投資は大きく勝つよりも「いかに市場に残り続けるか」が大事。自信過剰を避け、余計なことをせず、コツコツ積み立てることが、長期投資で成功する秘訣です。
5. 投資を継続できない理由5:SNSやメディアの“煽り”に流されてしまう
インデックスは買うな! オルカンはダメだ!?
近年は証券会社や民間企業もYouTubeなどで情報発信し、一部では「○○ファンドはもう古い」「インデックスは稼げないからやめろ」など、過激なタイトル・サムネイルで閲覧数(PV)を稼ごうとする動きが目立ちます。
投資初心者はどうしても「専門家っぽい人が言っているなら…」と真に受けがちで、結果的に自分の方針がブレてしまうのです。
短期的予想の的中率はあてにならない
いわゆる「アナリスト」や「専門家」と呼ばれる人が短期的株価や為替を予想しても、過去を振り返ると驚くほど当たらないケースが多々あります。
「○○ショックが来る」「今年は米国株が下落する」などと言われても、誰も1年先の相場を正確に予測できる人はいないと考えるのが妥当です。
投資初心者の方には、「専門家の肩書き=正確」という思い込みを捨て、必ず過去の発言や実績も確認する冷静さを持っていただきたいところです。
“煽り”を鼻で笑えるくらいの理解を
インデックスファンドの仕組みや歴史的リターンをしっかり理解している人であれば、「インデックスはゴミ!」といった極端な主張を見ても、「また煽っているな」とスルーできるようになります。
これができると、いちいち情報に振り回されず淡々と積み立てを継続できるので、結果的に長期で大きなリターンを得やすくなります。
6. 長期投資を成功させるための心構え
- 短期変動は当たり前
- シミュレーション通りに毎年資産が増え続けるなんてことはありません。上下変動を受け入れる覚悟が必要です。
- 含み損はむしろおいしい
- 長期前提なら、含み損は「安く買い増しできるチャンス」と捉えましょう。売却しなければ実損にはなりません。
- 投資対象を知る
- 目論見書や組入銘柄をざっと把握するだけでも安心感が違います。世界の大企業に投資するメリットを理解しましょう。
- 自信過剰を捨てる
- 自分は特別な存在ではない、と肝に銘じること。市場の平均を取るインデックス投資のほうが、むしろ安定的です。
- メディアの煽りに流されない
- 短期的予測は当たらないもの。派手なサムネイルやニュース速報に心を乱されず、コツコツ継続する姿勢を大切に。
7. まとめ
「長期投資をするぞ!」と決意したものの、いつの間にかやめてしまう主な理由は、以下の5つに集約できます。
- 毎年資産が増え続けると勘違いしている
- 含み損を現実の損失と捉えてしまう
- 投資対象への理解が不足している
- オーバーコンフィデンス(自信過剰)
- SNSやメディアの煽りに惑わされる
インデックス投資は、歴史的に見ても「最適解」と呼ばれるほど理にかなった方法です。それを超低コストで利用できる恵まれた時代を、私たちは生きています。
「上がっても下がっても楽しめる」のがインデックス投資の大きな利点です。上昇したら資産が増えるし、下落しても安く買い増せる。こうした柔軟な思考を身につけておけば、相場がどう動こうとポジティブに投資を継続できます。
最後に、投資の前提として生活防衛資金や近い将来使う予定のあるお金は投資に回さないという鉄則を忘れないでください。この鉄則を守るだけでも「大暴落が来たらどうしよう…」という不安は大きく軽減されます。
ぜひ今後も、インデックス投資を中心に合理的で堅実な資産形成を続け、経済的な自由や安心を手に入れていきましょう。