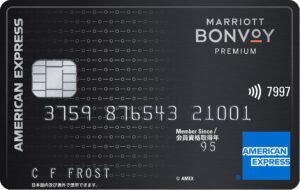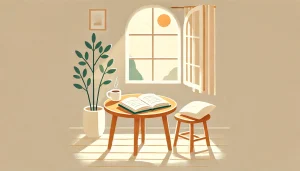みなさんこんにちは、わんだらです。今日はお金がある程度たまって余剰資金を投資に回せるようになると、どのように資産が雪だるま式に増えていくのかを解説していきます。実はこの現象、単なる感覚ではなく、経済学者のトマ・ピケティ氏が「R>G(アール・だいなり・ジー)」という法則で証明した事実に基づいています。
筆者はアラフォー会社員で、セミリタイアを目標に日々節約や投資に取り組んできました。その結果、資産4,000万円を達成し、「金融資産ピラミッド」におけるアッパーマス層に到達できました。実際に投資を続ける中で、この「R>G」という法則の威力を肌で感じることがしばしばあります。
今回は、そんな筆者の実体験を交えながら、
- トマ・ピケティの「R>G」とは何か
- なぜお金持ちはさらに豊かになり、格差が拡大してしまうのか
- 預貯金中心の日本人が陥りやすい落とし穴
- アメリカとの比較や、円安・インフレの影響
- 筆者のポートフォリオと実際の資産増加ペース
などを詳しく解説します。
1. R>Gとは?トマ・ピケティ氏が示した資本収益率の法則
トマ・ピケティ氏のプロフィール
- フランスの経済学者
- パリ経済学院の教授
- 過去300年分のデータを用いて、主に経済格差や富の再分配について研究
- 著書『21世紀の資本』(2013年発行)は世界的ベストセラーに
ピケティ氏は、膨大な歴史データをもとに「お金持ちはますますお金持ちに、貧しい人はなかなか豊かになれない」という格差拡大のメカニズムを分析しました。そしてそこから導き出された重要なキーワードが、R>Gです。
R>G(アール・だいなり・ジー)の意味
- R = 資本収益率(Return on capital)
- G = 経済成長率(Growth)
簡単に言えば、「投資や資本から得られるリターン(R)は、労働による経済成長(G)を上回り続ける」という法則です。ピケティ氏の調査によると、歴史的に見るとRは年間5%前後、Gは2%前後が平均値だとされています。
具体例
- 資本収益率(R):年利5%で運用する
- 例えば1億円を投資に回していれば、年間5%のリターン=500万円の不労所得が得られる計算になります。
- 経済成長率(G):年2%程度の賃金上昇
- 日本の平均年収約460万円が、毎年2%上がったとしても、上昇額は数万円程度。
このように、投資によるリターンが大きければ大きいほど、資産を持っている人がさらに富を増やすペースは加速し、結果的に格差が広がりやすい構造になるというわけです。
ピケティ氏自身は、この格差の拡大を是正するために金融所得に対する課税強化を提言しています。しかし、個人レベルで考える場合は、むしろこのR>Gの構造を味方につけることで、資産形成を加速できる可能性が高まります。
2. 日本とアメリカの資産形成の違い:貯金主義の落とし穴
アメリカは資産の85%をリスク資産で保有
アメリカの個人が保有する金融資産のうち、約85%が株式や保険などのリスク資産です。歴史的に株式市場が成長してきた背景もあり、投資によって資産を増やす文化が根付いています。
日本は預貯金が半数以上を占める
一方、日本の個人金融資産の約55%が預貯金。低金利の環境下で、銀行に預けていてもほとんど増えないのが現状です。これは言い換えると、「日本円に投資している」状態といえますが、インフレや円安が進行すると、その価値は相対的に目減りします。
貯金主義が生まれた歴史的背景
- 戦後の復興期:政府には資金が不足していたため、国民からの預貯金を活用してインフラを整備。
- 高度経済成長期の金利7%:郵便貯金など、当時は貯金するだけでお金が増えるイメージが強かった。
- バブル崩壊後の長期不況:日経平均株価が低迷し、投資はギャンブルという悪いイメージが刷り込まれた。
こうした歴史のなかで、日本人の大多数は「貯金は美徳」「投資は危険」という固定観念を持つようになったのです。
3. 投資を避けること自体がリスク?インフレ・円安時代の現金の価値
インフレ時代の現金の危うさ
インフレが進むと、物価は上がりお金の価値が下がります。銀行預金の金利がほぼゼロである以上、現金を持ち続けることで実質的な資産価値が減ってしまうのです。これに気づかず、長期間まとまった資金を寝かせてしまうと、将来「思っていたほどお金の価値がない」という事態に陥るかもしれません。
円安による国際的な価値下落
近年の円安傾向も懸念材料です。日本円の価値が下がると、ドルやユーロ建て資産との比較で相対的に不利になります。海外資産(外国株式や債券など)への投資をしておけば、円安による資産価値の下落リスクをある程度ヘッジできます。
「リスクを取らないことがリスク」
「リスクを取りたくないから投資しない」という声もよく聞きます。しかし、何も投資をしない=円のまま持ち続けることが、本当に安全なのでしょうか。インフレが続けば、その価値はどんどん目減りしていきます。投資の世界では「リスクプレミアムは、リスクを取らない人が支払ってくれている」という有名な言葉がありますが、まさにこのことを指しています。
4. 労働収入vs資本収益:実際にどれくらい差がつくのか
先進国の平均賃金推移
過去20年の先進国の平均賃金を日本(100%)とした場合、他国は約120~150%まで伸びています。たとえば韓国は約150%まで上昇し、3万ドルだった平均賃金が4.5万ドルになったというデータも。
これは確かに大きな伸びですが、年利5%で20年運用すれば資産は3倍近くになります。しかも投資によるリターンは「不労所得」であり、労働時間を増やす必要がありません。労働は大切ですが、資産形成という観点からは、投資が非常に効率的な手段だとわかります。
5. 筆者の実体験:投資によって“もう1人会社員が増えた”ような効果
ここからは筆者自身の体験談です。アラフォー会社員として働きながら、節約・投資をコツコツ続けることで、2022年には資産4,000万円を達成しました。
ポートフォリオの内訳
- 株式・投資信託・年金などのリスク資産:全体の67%
- 現金比率:32%
現金を多めに持っているのは、株式市場の暴落時に追加投資をするための“待機資金”を確保しているためです。将来的には、生活防衛資金(約500万円)を除く部分は、さらにリスク資産へシフトする予定です。
労働収入と投資収入の比較
- 年間の可処分所得(労働+副業)から支出を引いた残額:24万円
- 投資を含めた最終的な資産増加:約700万円(1年で3,350万円→4,069万円)
つまり、24万円が純粋な労働ベースでの増加分、残りの約462万円が投資によるリターンという計算になります。日本の平均年収に近い金額が“もう1人の会社員”として家計を助けてくれるわけです。これこそ、まさにR>Gの威力を実感した瞬間でした。
6. 企業型確定拠出年金の運用状況から見る格差の実態
企業型確定拠出年金とは?
- 企業が従業員の年金口座に掛金を拠出
- 従業員が投資商品を選び、運用の成果によって将来の年金額が変わる
元本保証型の定期預金のような商品から、外国株式・債券などのリスク資産まで、幅広いラインナップが用意されています。
全加入者の運用利回りの分布
筆者が利用している運用機関のデータによると、以下のような2極化がはっきり見られます。
- 元本保証型(約22%):運用利回りはほぼ0%
- 外国株式などのリスク資産型(約23%):運用利回りは10%以上
投資を選んだ人とそうでない人の間には、すでに大きな格差が生じています。まさにRを取るか取らないかで、将来の年金額に大きな差がつく一例といえるでしょう。
7. まとめ:R>Gを味方につけるために今できること
R>Gを理解し、資本収益を得る側に回ろう
- R>G(資本収益率>経済成長率)は歴史的に証明されてきた事実
- 投資による不労所得は、労働収入と比較して格段に効率の良い資産形成手段
リスクを取らないことは、むしろリスク
- 預貯金はほぼ金利ゼロ、インフレや円安で価値が下がる恐れ
- リスク分散として、海外資産(外国株や債券)も取り入れるのがおすすめ
日本人はすでに日本に「人的資本」を投資している
- 日本企業で働いている以上、給料は円建てで受け取ることが大半
- 金融資産の一部を海外へ向けることで、円安やインフレのリスクを軽減できる
実践するためにやるべきステップ
- 生活防衛資金の確保:数ヶ月~半年分の生活費を現金でキープ
- 余剰資金の投資:NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用
- 世界分散投資:日本株、米国株、新興国株、債券などをバランスよく保有
- 長期目線で継続:短期の値動きに一喜一憂せず、コツコツと積み立てる
終わりに
今回の記事では、「R>G」というキーワードを中心に、なぜ投資がお金持ちへの近道になるのか、その背景や具体的なデータをご紹介しました。筆者自身の経験からも、投資によって得られるリターンは想像以上に大きく、「もう1人会社員がいる」ような感覚を得ることができています。
- リスクを恐れて一切投資をしないのは、インフレや円安が進行している現代において、むしろ大きなリスクとなり得ます。
- 元本保証型の商品だけでは、預けているだけで実質的な価値が目減りする可能性が高いです。
- 海外資産への分散投資は、これからの時代、特に重要になるでしょう。
ぜひ、R>Gの考え方を参考に、資産形成の一歩を踏み出してみてください。労働収入を大切にしながらも、資本収益を得る“投資家”としての側面を持つことで、将来的な豊かさや安心感を得やすくなるはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が皆様の資産形成や投資の学びに少しでもお役立ちできれば幸いです。また次回の記事でお会いしましょう!